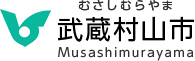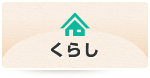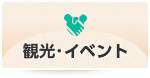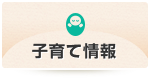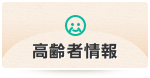令和6年度児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり児童手当制度が変わりました。
制度改正により申請が必要となる場合がありますので御確認ください。
|
改正点 |
旧制度(令和6年9月分まで) |
新制度(令和6年10月分から) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
支 給 額 |
3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降30,000円 | |
|
3歳から |
10,000円 |
第3子以降 |
10,000円 |
||
|
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
|||
|
高校生年代 |
支給対象外 |
10,000円 |
|||
|
所得制限 |
あり |
なし |
|||
|
算定対象児童 |
18歳到達後の年度末まで |
22歳到達後の年度末まで |
|||
|
支給月 |
4か月ごと(年3回) |
2か月ごと(年6回) |
|||
1.支給額の改定
月額(児童一人当たり)
3歳未満:15,000円(第3子目以降は30,000円)
3歳から高校生年代(18歳到達後の年度末まで):10,000円(第3子目以降は30,000円)
2.支給対象年齢の拡大
支給対象児童の年齢が中学生から高校生年代(18歳到達後の年度末まで)に延長されました。
「在学していない」「別居している」「就労している」等の場合でも対象となります。
ただし、受給者が当該子を養育している(日常的に面倒を見ており、生活費等を経済的に負担している)場合に限るため御注意ください。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
3.所得制限の撤廃
養育している父母等の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
4.算定対象児童年齢の拡大
制度改正により算定対象児童(手当の支給対象ではないが多子加算の対象として数えることができる子)の対象年齢が、高校生年代(18歳到達後の年度末まで)から大学生年代(22歳到達後の年度末まで)に延長されました。
ただし、受給者が子を養育している(日常的に面倒を見ており、生活費等を経済的に負担している)場合に限るため、御注意ください。(自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
(注)算定対象児童の上から数えて第3子目以降の子は、手当額が30,000円となります。
【例】21歳(大学生)、16歳(高校生)、11歳(小学生)の子を養育している場合
旧制度(令和6年9月分まで)
高校生年代(18歳到達後の年度末まで)が算定対象児童となるため、16歳(高校生)の子を第1子目、
11歳(小学生)の子を第2子目と数えて、手当額は11歳(小学生)の子の分の10,000円を支給する。
新制度(令和6年10月分から)
大学生年代(22歳到達後の年度末まで)が算定対象児童となるため、21歳(大学生)の子を第1子目、
16歳(高校生)の子を第2子目、11歳(小学生)の子を第3子目と数えて、手当額は16歳(高校生)の
子の10,000円、11歳(小学生)の子の30,000円の計40,000円を支給する。
5.支給月の変更
これまでの2月、6月、10月の年3回支給から、偶数月の年6回支給に変更されました。
申請方法
以下に該当するかたは申請が必要となります。
(1)所得超過により児童手当を受給していない
(2)高校生年代(18歳到達後の年度末まで)以上の子のみを養育している
(3)児童手当又は特例給付を申請していない
(4)大学生年代(22歳到達後の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を養育している
申請の要否についてはフローチャートも御確認ください。
現在、児童手当を受給している(フローチャートのAに該当する)かた
大学生年代(22歳到達後の年度末まで)の子から数えて3人以上の子を養育しているかたは、以下の書類を提出してください。
(注)父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)」を請求者としてください。
-
児童手当額改定認定請求書 (PDF 299.5KB)

-
児童手当額改定認定請求書(記入例) (PDF 325.4KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 117.1KB)

-
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 316.5KB)

現在、児童手当を受給していない(フローチャートのBに該当する)かた
これまで所得超過で受給資格がなかった、高校生年代(18歳到達後の年度末まで)以上の子しかいない等の理由から、児童手当を受給していなかったかたは、以下の書類を提出してください。
(注)父母等のうち「生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)」を請求者としてください。
児童手当認定請求書に加え、次の書類も必要です。
・請求者の口座がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
・請求者及び配偶者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
大学生の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて御提出ください。
その他、ケースにより追加で必要となる書類
請求者と支給対象児童が別居している場合
1月1日時点で、請求者・配偶者の住民票が日本になかった場合
パスポートの顔写真のページ及び出入国日がわかるページの写し
(注)1月1日時点は、申請月によって対象年が異なります。
- 申請月が1月から7月までの場合は前年の1月1日
- 申請月が8月から12月までの場合は当年の1月1日
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)![]() よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。